投資コラム
老後資金は4,000万円必要!?理想の貯蓄額をシミュレーション
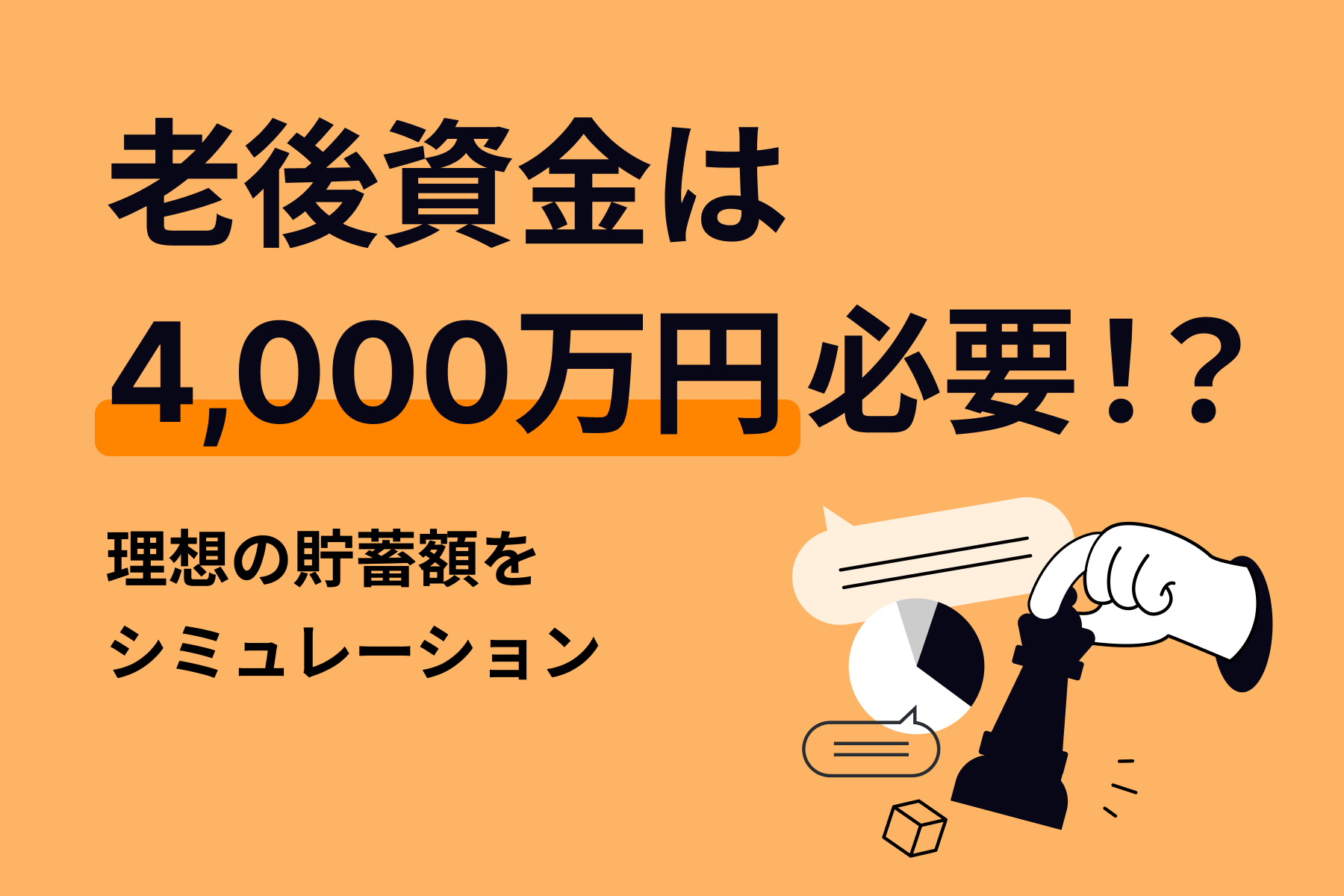
2019年に金融庁の報告書が公表され、老後2,000万円問題が一時話題になりました。 老後の不安を煽るショッキングな試算でしたが、最近になって「老後資産は4,000万円必要」とする考え方も出てきました。 とはいえ、「本当 […]
2019年に金融庁の報告書が公表され、老後2,000万円問題が一時話題になりました。
老後の不安を煽るショッキングな試算でしたが、最近になって「老後資産は4,000万円必要」とする考え方も出てきました。
とはいえ、「本当にそんな大金が必要なのか」「結局いくら貯めておけばいいのか」と疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、老後資金は4,000万円必要といわれている理由・背景をわかりやすく解説します。
現実的に必要な老後資金の計算方法や、効率よく資産形成するためのポイントなども紹介しているので、老後の暮らしに少しでも不安を感じている方は参考にしてみてください。
- 老後資金は本当に4,000万円になる?
⇒ 言い過ぎな側面もあるが、ひとつの目安として参考にしておくべき - 本当に必要な老後資金はいくら?
⇒ 年金の種類や資産状況、将来のライフプランを踏まえて計算する必要がある - 効率よく老後資金を貯めるにはどうすればいい?
⇒ 不動産クラウドファンディングなどを活用した資産運用がおすすめ!
目次
「老後資金4,000万円問題」とは?
まずは、「老後資金4,000万円問題」が話題になった背景や根拠について詳しくみていきましょう。
そもそも老後資金は2,000万円必要とする試算がある
「老後資金は4,000万円必要になる」との考え方は、老後2,000万円問題を前提にしています。
老後2,000万円問題とは、高齢夫婦世帯の生活費を年金だけで補うことはできず、老後30年間で約2,000万円が必要になるとする試算のことです。
2017年の家計調査データによると、高齢夫婦世帯の月収入が約21万円、支出が約26万円で約5.5万円の赤字が生じていたため、「5.5万円×12月×30年=約2,000万円」と試算されました。(参照:家計調査年報(総世帯・二人以上の世帯・単身世帯)|総務省)
もちろん、すべての世帯に当てはまる試算ではありませんが、メディアでも大々的に取り上げられ、多くの人々の不安を煽る出来事となったのです。
インフレが継続すると老後資金が4,000万円必要になる可能性も出てくる
「老後資金4,000万円問題」は2,000万円問題の試算をベースに、近年のインフレを考慮して算出されています。
試算は単純で、物価が3.5%のペースで20年間上昇し続けると仮定した場合、生活費が約2倍になるため、不足額も2,000万円から4,000万円に増えるというものです。
実際、消費者物価指数は上昇傾向にあり、月単位で3.5%を超えることも少なくありません。(参照:2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年(令和7年)6月分|総務省)
ケースバイケースとはいえども、老後4,000万円問題は決して的外れな試算ではないことを理解しておかなければなりません。
【注意】老後資金4,000万円は言い過ぎな側面もある
「老後資金4,000万円」は参考にするべき試算ではあるものの、言い過ぎな側面もある点に注意しておきましょう。
なぜなら、生活スタイルや家族構成、年金・退職金の額、持ち家か否かなどによって本当に必要な老後資金は大きく変動するためです。
また、急速な物価上昇率が今後も高止まりするとは言い切れません。
さらには、高齢夫婦無職世帯の赤字額が減少しているというデータもみられます。(参照:家計調査年報(家計収支編)|総務省)
「4,000万円」という数字だけにとらわれず、自分自身のケースに置き換えて、早い段階から資金計画を立てていくことが重要です。
貯蓄が4,000万円以上ある高齢者世帯の比率
総務省の調査によると、二人以上世帯のうち世帯主が65歳以上の貯蓄額は以下のとおりです。
| 貯蓄額 | 割合 |
| 100万円未満 | 8.1% |
| 100万円~300万円 | 6.7% |
| 300万円~500万円 | 9.9% |
| 500万円~700万円 | 6.2% |
| 700万円~1,000万円 | 8.6% |
| 1,000万円~1,400万円 | 9.4% |
| 1,400万円~2,000万円 | 11.7% |
| 2,000万円~2,500万円 | 7.4% |
| 2,500万円~3,000万円 | 5.8% |
| 3,000万円~4,000万円 | 9.4% |
| 4,000万円以上 | 20.0% |
(参照:家計調査報告(貯蓄・負債編)-2024年(令和6年)平均結果-(二人以上の世帯)|総務省)
貯蓄額が4,000万円を超えている世帯は2割にとどまります。
なお、合計値をデータ数で割った「平均値」は2,509万円、データを小さい順に並べたときの真ん中にあたる「中央値」は1,658万円です。
平均値は極端な富裕層の影響を受けるため、中央値の1,658万円を参考にしつつ、自分自身の貯蓄状況を客観的に分析してみるのがよいでしょう。
老後の収入・支出は一体いくらになるの?
次に、老後の収入・支出がいくらになるのか、具体的な金額をみていきましょう。
老後の収入|年金と退職金
老後の主な収入源は「年金」と「退職金」です。
それぞれどの程度の収入が見込めるのかを詳しく解説します。
年金:国民年金6万円・厚生年金15万円程度
年金受給額は、国民年金と厚生年金のどちらに加入しているかによって大きく異なります。
| 対象者 | 年金月額 | |
| 国民年金 | 自営業者・未就業者など | 57,700円 |
| 厚生年金 | 会社員・公務員 | 146,429円 |
ただし、実際の年金額は加入期間や納付状況にも左右されるので、あくまでもひとつの目安として捉えるようにしてください。
退職金:1,500万円~2,000万円程度
老後資金の柱となる退職金は、1,500万円~2,000万円程度が一般的です。(参照:令和5年賃金事情等総合調査|中央労働委員会)
とはいえ、退職金は勤務先の規模や勤務年数などによっても大きく変動します。
たとえば、大企業に長年勤めた場合は2,000万円以上もらえることもありますが、中小企業に務めていた場合や勤続年数が短い場合は1,000万円以下になるケースもあるでしょう。
会社の規定を確認すれば、退職金の見込みを立てることも可能です。
実際に受け取れる金額をしっかりと確認したうえで、老後に向けた生活設計に着手しましょう。
老後の支出|単身なら16万円・夫婦二人世帯なら29万円程度
老後の平均的な生活支出は単身世帯で月16万円前後、夫婦二人世帯なら月29万円前後が目安です。
| 消費支出 | 非消費支出(税金・社会保険料) | |
| 65歳以上の単身無職世帯 | 14万9,286円 | 1万2,647円 |
| 65歳以上の夫婦のみの無職世帯 | 25万6,521円 | 3万356円 |
(参照:家計調査(家計収支編)調査結果|総務省)
なお、上記の支出金額には、医療費・介護費・自宅修繕費などの費用が含まれていません。
実際には、より多くのお金が必要になるものと考えておくようにしましょう。
老後資金はいくら貯めればいい?不足額をシミュレーション
老後資金4,000万円はひとつの目安にはなるものの、本当に必要な額は人それぞれで異なります。
ここでは、会社員・自営業者が単身または夫婦二人で暮らす場合を想定し、老後の不足額をシミュレーションしてみます。
会社員が老後を迎えたときの不足額
まずは、会社員が老後を迎えたときの不足額をシミュレーションしてみましょう。
単身世帯の場合
会社員の場合は、月15万円程度の厚生年金を受給できます。
一方で、毎月の支出は16万円程度です。
つまり、「収入15万円 - 支出16万円 = -1万円」が毎月不足する計算になります。
よって、老後が25年あるとすると、「1万円 × 12月 × 25年 = 300万円」を貯めておく必要があります。
インフレが続くと数百万円単位の上乗せが必要になる可能性もありますが、1,000万円以上の退職金を受け取れるのであれば、不足分は十分補えるでしょう。
夫婦二人世帯の場合
夫婦二人世帯の場合、いずれかが会社員であれば少なくとも月15万円程度の厚生年金を確保できます。
そして、配偶者の加入する年金制度によって、世帯としての収入は大きく変わります。
- 配偶者が会社員の場合:配偶者の厚生年金15万円がプラス
- 配偶者が専業主婦・自営業者の場合:配偶者の国民年金6万円がプラス
上記の点を踏まえて、老後の不足額を計算すると以下のようになります。
| 収入 | 支出 | 月の不足額 | |
| 配偶者が会社員 | 15万円+15万円=30万円 | 29万円 | 30万円 – 29万円 = 1万円(不足なし) |
| 配偶者が専業主婦・自営業者 | 15万円+6万円=21万円 | 29万円 | 21万円 – 29万円 = -8万円 |
毎月の生活費に不足が生じるのは、会社員と専業主婦・自営業者の世帯です。
老後25年間で換算すると「8万円 × 12月 × 25年 = 2,400万円」が不足します。
会社員の退職金があることを考慮しても、別途老後資金を貯めておかなければ生活は苦しくなるでしょう。
自営業者が老後を迎えたときの不足額
次に、自営業者が老後を迎えたときの不足額をシミュレーションしてみましょう。
単身世帯の場合
自営業者の場合は、月6万円程度の国民年金を受給できます。
一方、毎月の支出は16万円程度なので、「収入6万円 - 支出16万円 = -10万円」が毎月の不足額です。
よって、老後25年を想定すると「10万円 × 12月 × 25年 = 3,000万円」を貯めておく必要があります。
加えて、自営業者は退職金がないので、老後資金の不足は会社員よりも深刻です。
夫婦二人世帯の場合
夫婦二人世帯の場合、いずれかが自営業者であれば、最低限月15万円程度の国民年金を受け取れます。
そして、配偶者の加入する年金制度によって、世帯としての収入は以下のように変動します。
- 配偶者が会社員の場合:配偶者の厚生年金15万円がプラス
- 配偶者が専業主婦・自営業者の場合:配偶者の国民年金6万円がプラス
上記の点を踏まえて、老後の不足額をシミュレーションしてみます。
| 収入 | 支出 | 月の不足額 | |
| 配偶者が会社員 | 6万円+15万円=21万円 | 29万円 | 21万円 – 29万円 = -8万円 |
| 配偶者が専業主婦・自営業者 | 6万円+6万円=12万円 | 29万円 | 12万円 – 29万円 = -17万円 |
老後25年間で換算すると、配偶者が会社員の場合は「8万円 × 12月 × 25年 = 2,400万円」が不足します。
配偶者が専業主婦・自営業者の場合は「17万円 × 12月 × 25年 = 5,100万円」
いずれにしても、自営業者は年金が少ないので、老後の不足額が大きくなりやすいです。
不足額を性格に算出したうえで、できるだけ早く老後資金の形成に着手することをおすすめします。
必要な老後資金は人それぞれ!加味しておくべき要素
必要な老後資金を算出する際には、以下の3点を考慮することで、より精度が高まります。
- 何歳まで働くのか
- 持ち家はあるか
- どの程度の生活水準を求めるのか
老後の生活を具体的にイメージし、現実的な老後資金を算出することが大切です。
何歳まで働くのか
老後資金の必要額は、何歳まで働くかによって大きく変わります。
就労期間が延びれば延びるほど収入が増えるので、その分、老後の不足額は減少します。
また、公的年金の受給開始年齢を遅くすれば、年金総額が増えるため、老後の生活は楽になるでしょう。
近年では、定年後も再雇用やパートなどで働くことが当たり前になっているので、自身の体調や会社の雇用状況も踏まえたうえで、シミュレーションすることが重要です。
持ち家はあるか
持ち家の有無も、老後資金を大きく左右する要因のひとつです。
持ち家があれば家賃負担が発生せず、老後の固定費を抑えられます。
一方、賃貸の場合は、毎月数万円~数十万円の負担が上乗せされるため、老後に必要な資金が大幅に増加してしまうのです。
家賃は支出に占める割合が大きいため、老後資金をシミュレーションする際には必ず考慮するようにしてください。
ただし、持ち家の場合でもリフォーム費や固定資産税などがかかってくる点に注意が必要です。
どの程度の生活水準を求めるのか
どの水準の生活を目指すかによっても、必要な老後資金は大きく変動します。
上述のとおり、一般的な老後の支出は単身で月16万円、夫婦二人世帯で月29万円です。
しかし、旅行や趣味などを楽しめる程度のゆとりある生活を送る場合には、より多くの資金が求められます。
生命保険文化センターの調査によると、ゆとりある生活を送るには月38万円程度の生活費が必要になるともいわれています。(参照:2022(令和4)年度 生活保障に関する調査|公益財団法人生命保険文化センター)
仕事に縛られない、自由気ままな老後の生活を心待ちにしている人も少なくないはずです。
少しでも豊かな生活を実現できるように、資産形成を積極的に進めるようにしましょう。
効率的に老後資金を形成するなら資産運用が重要!
シミュレーション結果からもわかるように、老後資金はまとまったお金が必要です。
そのため、銀行預金だけではなく、積極的な資産運用によって効率的に老後資金を形成していくことをおすすめします。
初心者におすすめの資産運用3選
資産運用を成功させるには、最低限の知識と経験が必要になります。
初心者がいきなりハイリスク・ハイリターンの運用を始めると、痛い目をみることになるので注意しておきましょう。
ここでは、初心者におすすめの資産運用を3つ紹介するので参考にしてみてください。
不動産クラウドファンディング
不動産クラウドファンディングは、オンライン上で不特定多数の投資家から集めた資金を元手に、事業者が不動産を購入・運用する仕組みのことです。
投資家には出資額に応じて、運用益の一部が還元されます。
不動産クラウドファンディングの特徴は、初心者には難しい不動産経営を事業者に任せられる点です。
不動産や投資の知識がなくても、十分な運用益を得ることができます。
また、1万円程度から出資できるため、無理なく始められるのも大きなメリットといえるでしょう。
不動産クラウドファンディングサービスはいくつかありますが、なかでもおすすめなのは不動産BANKです。
不動産BANKでは、利益が出やすい首都圏の中古物件を取り扱っており、安定して年6%の高利回りを実現しています。
随時、魅力的なファンドが立ち上がっているので、興味がある方は公式サイトをチェックしてみてください。
投資信託
投資信託は、投資家から集めた資金をもとに、投資のプロが株式や債券などを運用する金融商品のことです。
投資家に対しては、保有額に応じて運用益が分配されます。
投資信託では事業者に運用を任せられるので、ほぼ手放しで運用益を受け取ることが可能です。
また、証券会社によっては100円からでも投資できるため、初心者には最適の資産運用といえるでしょう。
ただし、投資信託では、プロに運用を代行してもらうための手数料「信託報酬」が必要です。
投資信託を保有している限り、年率0.5%~2.5%程度の信託報酬が発生するので、できるだけ信託報酬率が低い銘柄を選ぶようにしましょう。
個人向け国債
個人向け国債は、財源確保のために国が発行する債券のことです。
満期まで保有していれば、元本満額に利息が上乗せされて返ってきます。
購入後1年経過すれば途中解約が可能であり、利息は減額されますが、それでも元本割れしない点が国債の魅力といえるでしょう。
なお、個人向け国債は金利タイプや満期に応じて、以下の3種類に分かれています。
| 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 | |
| 満期 | 3年 | 5年 | 10年 |
| 金利タイプ | 固定金利 | 変動金利 | |
| 金利の下限 | 0.05% | ||
| 利子の受け取り | 年2回 | ||
| 購入単価 | 1万円単位 | ||
ただし、個人向け国債の金利は預貯金よりもやや高い程度です。
近年、金利が上昇しているとはいえ、それでも1%前後にとどまります。
そのため、個人向け国債は、必要最小限のリスクで着実に利息収入を得たい方に適した投資先といえるでしょう。
資産運用を始める際は公的制度を活用しよう
資産運用の効果を最大化するには、公的制度の活用が必須です。
公的制度を活用すれば、税金の優遇メリットを受けながら、自分に合った投資スタイルで効率よく資産を増やせます。
主にNISAとiDeCoの2種類が挙げられるので、それぞれの特徴を詳しくみていきましょう。
NISA
NISAは、少額での投資を後押しするために作られた非課税制度です。
日本に住む18歳以上であれば、基本的に誰でもNISAを利用できます。
NISAのメリットは、投資で得た利益に一切税金がかからなくなることです。
通常であれば20.315%の税金が差し引かれるので、100万円の利益が出ても、約80万円しか受け取れません。
しかし、NISA口座で取引するだけで、100万円をそのまま受け取れるようになるのです。
なお、NISAは投資対象や年間の投資枠によって「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つに分かれています。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限 | |
| 非課税保有限度額 | 総枠1,800万円(成長投資枠に限っては1,200万円が上限) | |
| 投資対象 | 投資信託 | 株式・投資信託など |
まずは、投資信託でコツコツ利益を積み上げたいのであれば「つみたて投資枠」、株式を含めてさまざまな投資商品で資産運用したいなら「成長投資枠」がおすすめです。
「つみたて投資枠」と「成長投資枠」は併用も可能なので、投資スタイルに応じて使い分けるのもよいでしょう。
iDeCo
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、将来の年金を自助努力で増やしたい人向けの私的年金制度です。
iDeCo口座を通じて毎月一定額を拠出し、60歳以降に元本と運用益を受け取れます。
国民年金の被保険者であれば、基本的に誰でも加入可能です。
iDeCoを利用するメリットは、NISAと同様に運用益が非課税になる点です。
約20%の税金を回避できるので、無駄なく資産形成を進められます。
また、掛金が全額所得控除される点もiDeCoの魅力といえるでしょう。
拠出額を所得から差し引けるので、その分、所得税・住民税の節税効果が期待できます。
たとえば、年収500万円の人が毎月2万円を拠出すれば、所得税・住民税を年間で2万4,000円ずつ節税できる計算です。
ただし、60歳になるまでは資金を引き出せないので、老後資金専用口座と割り切って、無理のない範囲で拠出額を設定するようにしましょう。
なお、iDeCoの拠出上限額は、自営業、会社員・公務員、専業主婦(主夫)のどれに該当するかによって異なります。
会社員の場合は、企業型DC・DBへの加入状況によっても上限が変動するので、あらかじめiDeCoの公式サイトなどで拠出可能額を確認しておくようにしましょう。
まとめ
「老後資金は4,000万円必要」との試算は言い過ぎな側面もありますが、ひとつの目安として参考にするべき指標です。
実際、今の日本ではインフレが急速に進んでいるため、計画的に資産形成を進めなければ、十分な老後資金を確保できない可能性があります。
とはいえ、4,000万円もの大金を銀行預金だけで貯めていくことは簡単ではないでしょう。
そのため、ある程度のリスクをとりながらも、積極的に資産運用を進めていくことが重要です。
これから老後を見据えて資産運用を始めるのであれば、不動産クラウドファンディングをおすすめします。
少額から投資できるうえ、不労所得に近いかたちで運用益を得られるので、本業が忙しい方でも無理なく始められるでしょう。
不動産クラウドファンディングに興味がある方は、ぜひ不動産BANKの公式サイトをチェックしてみてください。
不動産BANKでは、年6%の高利回りを狙えるファンドがラインナップされています。
気になるファンドが見つかった際にすぐ応募できるように、まずは会員登録だけでも済ませてみてはいかがでしょうか。



