投資コラム
資産3,000万円あれば精神的余裕を得られる?資産形成のポイントも解説
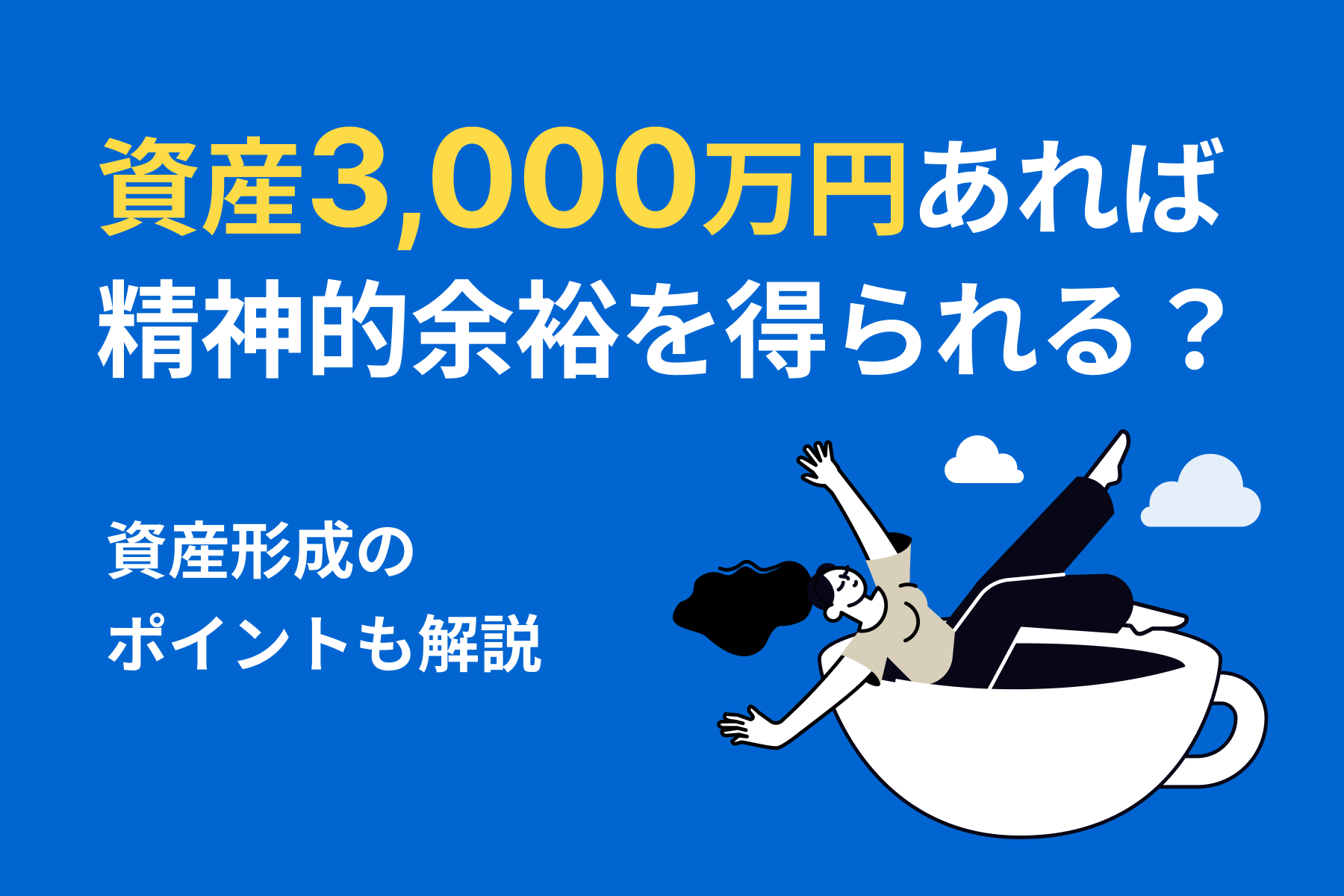
目次資産3,000万円を達成したときに得られる精神的余裕とは?資産3,000万円を保有している人の割合は約1割資産3,000万円に向けた道のりをシミュレーション資産3,000万円で精神的余裕を得るためのポイント資産3,0 […]
目次
日常生活を送るなかで、誰しもがお金に関する悩みを抱えています。
近年では急激な物価上昇や年金問題が騒がれることも多いので、自らの資産状況に不安を感じている方も少なくないはずです。
実際、目指すべき資産額は個々の状況によって異なります。
その中で、キリよく3,000万円を達成した場合、日々の生活はどのように変化するのでしょうか。
本記事では、資産3,000万円を達成したときに得られる精神的余裕について解説します。
資産3,000万円を達成するための条件や効率的な運用方法なども紹介するので、ぜひ最後まで目を通してみてください。
- 資産3,000万円を達成すると人生はどう変わる?
⇒ 生活が安定し、仕事の自由度が高まるなど精神的余裕が出る - 資産3,000万円を保有している割合は?
⇒ 約1割にとどまるのが実情 - 資産3,000万円を達成するにはどうすればいい?
⇒ 不動産クラウドファンディングなどの資産運用を始めるのがおすすめ!
資産3,000万円を達成したときに得られる精神的余裕とは?

資産3,000万円を達成すれば、以下のような変化が生じ、精神的余裕を持った生活が送れるようになります。
- 生活が安定する
- 仕事の自由度が高まる
- 早期リタイア・セミリタイアが選択肢に入る
資産3,000万円で人生がどのように変化するのか、具体的にみていきましょう。
生活が安定する
資産3,000万円を形成できれば、生活の安定感が格段に高まります。
なぜなら、急な出費や失業などの予期せぬ出来事にも慌てずに対応できるからです。
たとえば、家電が突然壊れてしまった場合や高額な医療費が生じた場合でも、3,000万円あれば、資産に占める出費の割合はそれほど大きくなりません。
また、旅行や趣味などにもお金を回せるようになるので、心の豊かさや充実感にもつながるでしょう。
資産管理にさえ注意しておけば、よほどのことがない限り、長期的に安定した生活を維持できます。
仕事の自由度が高まる
3,000万円の資産を築けると、仕事の自由度も高まります。
生活費の一部を資産から補える安心感があるため、収入だけに縛られず自分らしいキャリアを追求しやすくなるのです。
たとえば、長年勤めた会社から転職したり、フリーランスに転身したりするなど、思い切った選択が可能になります。
また、働く環境を見直せば、心身の健康を守ることも可能です。
仕事は人生のなかでも大きなウエイトを占めるものなので、自由度が高まることは大きなメリットといえるでしょう。
早期リタイア・セミリタイアが選択肢に入る
資産3,000万円を達成したあとは、早期リタイアやセミリタイアも現実的な選択肢に入ってくるでしょう。
3,000万円もの資産があれば、それだけである程度の生活費をまかなうことができます。
加えて、資産運用がうまくいけば、不労所得でまとまった金額を得ることも十分可能です。
結果として、40代・50代で仕事の比重を減らし、自分や家族の時間を大切にしたり、地域活動やボランティアに励んだり、自由な時間を使って心豊かな生活を送れるようになります。
もちろん必要な生活費は人それぞれ異なりますが、少なくとも、ゆとりあるセカンドライフが目の前にあることは確かです。
関連記事:普通の会社員でもセミリタイアできるって本当?必要な資金や投資方法
資産3,000万円を保有している人の割合は約1割

金融広報中央委員会の調査によると、資産3,000万円を保有している人の割合は約1割にとどまります。
年代別にみた資産3,000万円以上の割合は、以下のとおりです。
| 世帯主の年齢 | 資産3,000万円以上の割合 |
| 20代 | 0.1% |
| 30代 | 4.0% |
| 40代 | 6.0% |
| 50代 | 10.7% |
| 60代 | 19.0% |
| 70代 | 18.9% |
(参考:(参考)令和5年(2023年)家計の金融行動に関する世論調査[総世帯]|金融広報中央委員会)
基本的には、長期的な資産形成を着実に続けてきた高齢世帯、高年収層、大きな相続などを受けた方などが資産3,000万円に達しているものと考えられます。
20~40代で資産3,000万円以上保有している世帯は限られており、簡単に達成できる金額ではないことがわかるでしょう。
資産3,000万円に向けた道のりをシミュレーション

ここでは、資産3,000万円に向けた道のりを具体的にみていきましょう。
世帯別・収入別にシミュレーションしているので、参考にしてみてください。
単身世帯の場合
単身世帯の場合、消費支出の平均額は約17万円です。(参考:家計調査(家計収支編) 調査結果|総務省統計局)
毎月の収入額に応じて、資産3,000万円までの年数をシミュレーションすると以下のようになります。
| 毎月の収入額 | 資産3,000万円に達するまでの年数 |
| 30万円(年収360万円) | 3,000万円÷(30万円-17万円)=約230ヵ月 →約19年 |
| 50万円(年収600万円) | 3,000万円÷(50万円-17万円)=約90ヵ月 →約7年 |
| 70万円(年収840万円) | 3,000万円÷(70万円-17万円)=約56ヵ月 →約5年 |
民間給与の中央値は約400万円とされています。(参考:民間給与実態統計調査結果|国税庁)
ライフスタイルにもよりますが、毎月堅実に貯金を進めたとしても、資産3,000万円を達成するには10年以上を要する人が多いといえるでしょう。
二人以上世帯の場合
二人以上世帯の場合、消費支出の平均額は約30万円です。(参考:家計調査(家計収支編) 調査結果|総務省統計局)
毎月の収入額に応じて、資産3,000万円までの年数をシミュレーションすると以下のようになります。
| 毎月の収入額 | 資産3,000万円に達するまでの年数 |
| 50万円(年収600万円) | 3,000万円÷(50万円-30万円)=約150ヵ月 →約13年 |
| 70万円(年収840万円) | 3,000万円÷(70万円-30万円)=約75ヵ月 →約6年 |
| 90万円(年収1,080万円) | 3,000万円÷(90万円-30万円)=約50ヵ月 →約4年 |
民間給与の中央値が約400万円であることを踏まえると、夫婦共働き世帯であれば、10年足らずで資産3,000万円を達成できます。
とはいえ、実際には冠婚葬祭費や進学費などの突発的な支出が生じたり、出産・子育期間中に収入が減少したりするケースも少なくありません。
現実問題、コツコツ貯蓄を積み上げたとしても、数年で3,000万円もの資産を形成することは簡単ではないでしょう。
資産3,000万円で精神的余裕を得るためのポイント

資産3,000万円で精神的余裕を得るためには、以下のポイントを意識しておくことが重要です。
- 毎月の収支を正確に把握する
- 目標を具体的に設定する
- 固定費を見直す
- 先取貯蓄を徹底する
- 資産運用に取り組む
効率的な資産形成に欠かせないポイントばかりなので、それぞれ詳しくみていきましょう。
毎月の収支を正確に把握する
資産3,000万円を目指す際は、まず毎月の収入・支出を正確に把握することから始めましょう。
収支を把握することで、どの程度お金に余裕があるのかが明確になるので、計画的に資産形成を進められるようになります。
また、定期的に家計をチェックしておけば、資産形成のペースや問題点にも気づきやすくなるでしょう。
収支を管理する際は、家計簿アプリの利用をおすすめします。
日々の支出がひと目でわかり、手間をかけずに済むので、途中で投げ出すこともなくなるはずです。
目標を具体的に設定する
資産形成を続けるためには、あらかじめ目標を設定しておくことも大切です。
明確なゴールが見えていれば、計画が立てやすいだけでなく、モチベーションの維持にもつながります。
「何年後に3,000万円を達成する」「毎月いくら貯蓄する」といったように、できるだけ具体的に目標設定することを心がけましょう。
また、家族やパートナーと目標を共有すれば、協力して資産形成を進めやすくなります。
固定費を見直す
固定費を見直すだけでも、資産3,000万円までの道のりは大幅に短縮されます。
支出のうち、固定費が占める割合は大きくなりがちです。
無駄に固定費を支払っていることも多いので、一度見直す機会を設けるようにしてください。
具体的には、以下のような固定費の削減方法が考えられます。
- 家賃:収入に見合った住居への引っ越し
- 光熱費:料金プランの切り替え、省エネ家電への買い替え
- 通信費:格安SIMへの乗り換え
- 保険料:不要な保険の解約、より安い保険会社・商品への切り替え
- サブスクサービス:不要なサービスの解約
固定費の削減は即効性があり、節約した分を貯蓄や運用に回せるため、継続的に見直しをおこないましょう。
先取貯蓄を徹底する
先取貯蓄を徹底することも、資産を効率よく増やすためのポイントといえるでしょう。
先取貯蓄とは、給与が振り込まれた際に貯蓄分を先に確保する方法のことです。
無駄遣いや浪費を抑えられるので、着実に資産形成を進められるようになります。
給料日がくるたびに入出金していると面倒なので、財形貯蓄や積立定期預金を活用してみてください。
資産運用に取り組む
資産3,000万円を目指すのであれば、単なる預金だけでなく、資産運用の力も活用しましょう。
日本の金利は上昇傾向にあるものの、利息で得られる収入は微々たるものです。
一方で、余剰資金を運用に回せば、高い利回りで加速度的に資産を増やしていくことができます。
たとえば、銀行預金では年利1%にさえ満たないケースがほとんどですが、資産運用に取り組めば初心者でも5%程度なら十分狙えるでしょう。
ただし、資産運用は損失のリスクがともなうものです。
元本割れする可能性があることを前提に、「少額で始める」「無理にハイリターンを狙わない」などリスク管理を徹底しておきましょう。
資産3,000万円を目指す際におすすめの資産運用5選

資産3,000万円を目指す際におすすめの資産運用は以下の5つです。
- 不動産クラウドファンディング
- 投資信託
- 株式投資
- 不動産投資
- 個人向け国債
各運用方法のメリット・デメリットを詳しく解説します。
不動産クラウドファンディング
不動産クラウドファンディングは、不特定多数の投資家からオンライン上で集めた資金を元手に、事業者が不動産を購入・運用する仕組みのことです。
投資家は出資額に応じて、運用益の一部を受け取ることができます。
不動産クラウドファンディングのメリットは、不動産の運用を事業者に一任できる点です。
投資家がやることは定期的に運用益をチェックする程度なので、投資や不動産の知識がなくても安定した収入を得ることができます。
また、1万円程度から出資できるため、少額で投資経験を積みたい初心者に適した方法といえるでしょう。
ただし、あらかじめ定められた運用期間を終えるまでは、原則として中途解約できない点に注意してください。
長ければ1年以上資金が拘束されるので、無理のない範囲で出資額を決めることが大切です。
不動産クラウドファンディングサービスはいくつかありますが、これから始めるのであれば不動産BANKをおすすめします。
不動産BANKでは利益が出やすい首都圏の中古不動産を中心に取り扱っており、安定して高利回りを実現しています。
気になる方は、ぜひ公式サイトをチェックしてみてください。
投資信託
投資信託は、投資家から集めた資金をもとに、資産運用のプロが株式や債券などを運用する金融商品です。
投資家は保有量に応じて、分配金を受け取ることができます。
証券会社によっては100円程度から購入できるので、資金力に余裕がなくても気軽に始められるはずです。
また、投資信託の各銘柄は複数の投資先で構成されています。
そのため、ひとつの銘柄を購入するだけで、簡単に分散投資ができるのも大きなメリットといえるでしょう。
ただし、投資信託では、プロに運用を任せるための手数料「信託報酬」が発生します。
保有額の一定割合を支払い続けることになるので、できるだけ信託報酬率が低い銘柄を選ぶのがポイントです。
株式投資
株式投資は、資金調達のために企業が発行する株式を取引して、利益を狙う手法のことです。
安く買って、高く売った分だけ利益になります。
また、定期的に配当金が付与されるため、不労所得を形成することも可能です。
最近では、株主優待が充実している銘柄も多いので、銘柄選びの際にチェックしておくとよいでしょう。
なお、株式の購入単位は基本的に100株であり、少なくとも10万円程度の資金は必要です。
余剰資金が少ない場合は、1株から購入できる単元未満株を有効に活用してください。
不動産投資
不動産投資は、戸建やマンションなどを購入し、貸し出すことで家賃を得る手法のことです。
物件が値上がりしていれば、売却時に莫大な利益が出ることもあります。
不動産投資のメリットは、銀行から融資を受けられる点です。
資金力に乏しくても、大きな金額を動かして、ハイリターンを狙うことができます。
ただし、経営がうまくいかなければ借金を背負う可能性があるほか、災害時や大規模修繕時には多額の費用を要するので、比較的リスクが高い手法といえるでしょう。
また、不動産投資では物件選びが何よりも重要です。
物件の下調べや収支シミュレーションをおろそかにした状態で投資すると、痛い目をみることになります。
個人向け国債
個人向け国債は、財源確保のために国が発行する債券を購入し、利息を得る投資手法です。
満期まで保有していれば、元本がそのまま返還されるので、利息の分だけ利益が生じます。
購入してから1年経過すると中途解約も可能であり、利息は減るものの、元本割れすることはありません。
個人向け国債は満期や金利タイプによって3種類に分かれているので、自身の運用方針に合わせて適切に使い分けましょう。
| 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 | |
| 満期 | 3年 | 5年 | 10年 |
| 金利タイプ | 固定金利 | 変動金利 | |
| 金利の下限 | 0.05% | ||
| 利子の受け取り | 年2回 | ||
| 購入単価 | 1万円単位 | ||
個人向け国債のデメリットは、リターンが小さいことです。
年利は発行時期によって異なりますが、高くても1%程度なので、短期間で大きなリターンを狙いたい人には不向きといえるでしょう。
資産3,000万円を目指す際に活用するべき公的制度

資産3,000万円を目指す際には、公的制度を積極的に活用しましょう。
主にNISAとiDeCoの2つが挙げられるので、それぞれの制度概要を詳しく解説します。
NISA
NISAは、少額での投資を後押しするためにつくられた公的制度です。
日本在住の18歳以上であれば、基本的に誰でもNISA口座を開設できます。
NISAを利用するメリットは、投資による利益が一定枠まで非課税になる点です。
通常、投資の利益には20.315%の税金がかかります。
仮に10万円の利益が出ても、手元に残るのは約8万円だけです。
一方、NISA口座で投資していれば、10万円をそのまま受け取ることができます。
NISAは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2種類に分かれており、年間で投資できる上限額や投資対象に以下のような違いがあります。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限 | |
| 非課税保有限度額 | 総枠1,800万円(成長投資枠に限っては1,200万円が上限) | |
| 投資対象 | 投資信託 | 株式・投資信託など |
投資信託メインで運用したいなら「つみたて投資枠」、株式を含めてさまざまな投資商品にチャレンジしたいなら「成長投資枠」が適しています。
資金に余裕がある方は「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を併用するのがおすすめです。
iDeCo
iDeCoは、老後の資産形成を効率的に進められる私的年金制度です。
毎月定額を拠出し、解約時に掛金総額と運用益を受け取ることができます。
20歳以上60歳未満の国民年金被保険者であれば、原則として誰でも加入可能です。
iDeCoを利用するメリットは、大きく分けて2つあります。
1つ目は、NISAと同様に運用益が非課税になる点です。
約20%の課税を回避できるので、無駄なく資産を積み上げていくことができます。
2つ目は、掛金を全額所得控除できる点です。
1年間で拠出した分だけ所得額から差し引けるので、所得税や住民税の節税につながります。
ただし、iDeCoの資産を受け取れるのは、原則として60歳以降です。
緊急時にもiDeCoの資産はあてにできないので、余裕をもって拠出額を設定するようにしてください。
まとめ

資産3,000万円を達成できれば、精神的余裕のある日々を送れるようになります。
生活が豊かになり、仕事の自由度も高まるので、人生の選択肢は大きく広がるでしょう。
しかし、資産3,000万円を手にするのは簡単なことではありません。
収入にもよりますが、単に貯金しているだけでは、何十年も先のことになる可能性があります。
資産3,000万円までの道のりを短縮したいのであれば、資産運用に取り組み、効率的にお金を増やしていくことが重要です。
これから資産運用を始めるのであれば、不動産クラウドファンディングをおすすめします。
不動産クラウドファンディングは少額で出資できるうえ、ほぼ手放しで運用益を得られるので、初心者の方には特に適した方法といえるでしょう。
少しでも不動産クラウドファンディングに興味がある方は、不動産BANKの公式サイトをチェックしてみてください。
不動産BANKでは、年利6%を狙える魅力的なファンドが随時立ち上がっています。
すべての手続きはオンライン上で完結できるので、まずは会員登録だけでも済ませてみてはいかがでしょうか。



