投資コラム
少額投資とは?初心者におすすめな手法や失敗しないポイントを解説
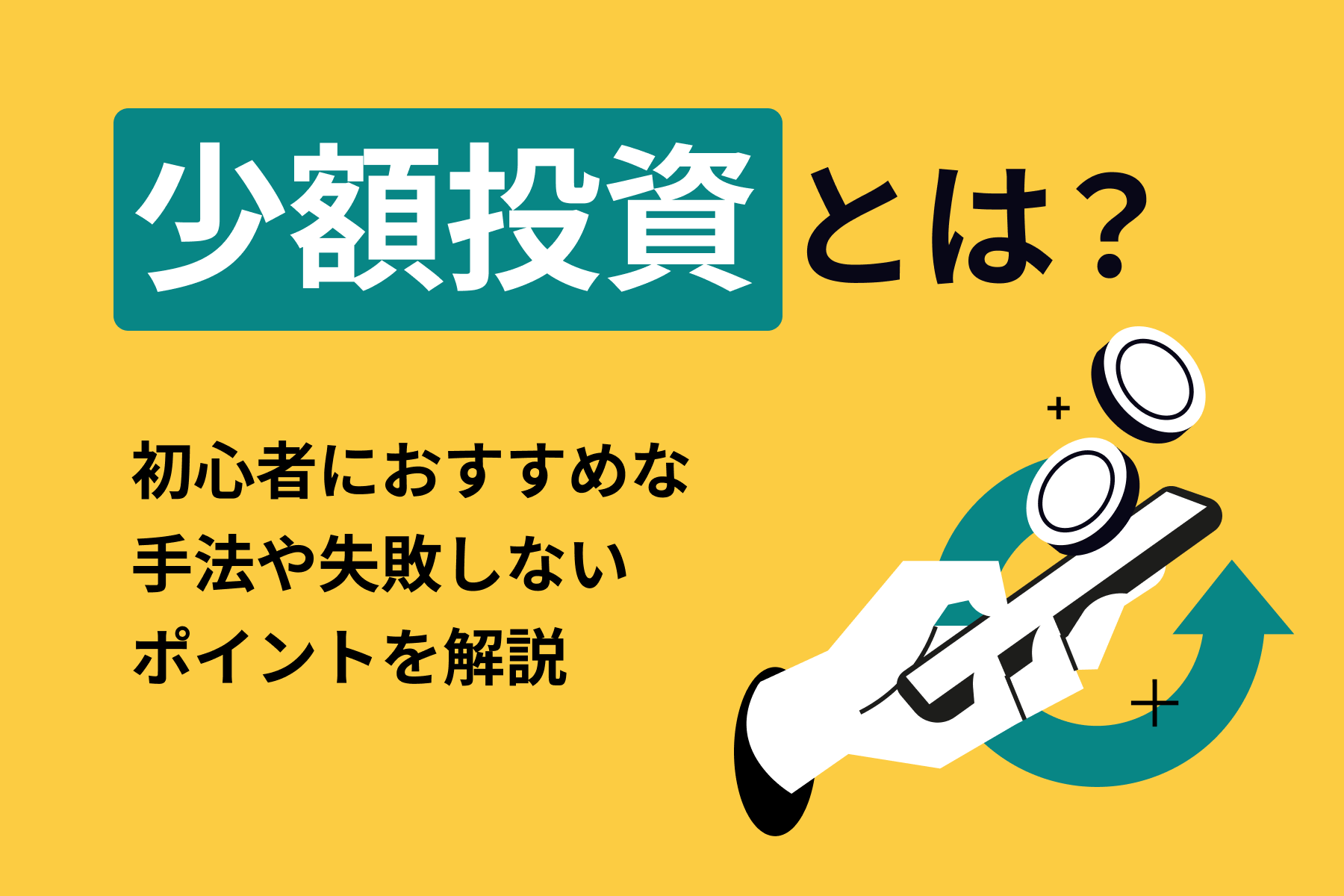
投資で利益を上げるためには、なによりもリスク管理が重要といえます。 リスク管理の方法は多岐にわたりますが、なかでも簡単に実践できるのが少額投資です。 そもそもの投資額を少額にとどめておけば、損失のダメージも最小限に抑えら […]
投資で利益を上げるためには、なによりもリスク管理が重要といえます。
リスク管理の方法は多岐にわたりますが、なかでも簡単に実践できるのが少額投資です。
そもそもの投資額を少額にとどめておけば、損失のダメージも最小限に抑えられます。
実際に「まずは少額から投資にチャレンジしてみたい」「できるだけリスクを取らずに投資経験を積みたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、少額投資のメリットや具体的な手法について解説します。
少額投資で失敗しないためのポイントなども詳しくまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
- 少額投資のメリットは何?
⇒ 損失のリスクを抑えて、投資の実践経験を積めること! - 少額投資に適した投資手法は?
⇒ 不動産クラウドファンディングや投資信託などがおすすめ! - 少額投資を成功させるためのポイントは?
⇒ 事前に目標を立てて、長期的な視点で取り組むことが重要!
少額投資は10万円以下でできる資産運用のこと

一般的に、少額投資は10万円以下の少額から始められる資産運用のことを指します。
まとまった資金がなくても、気軽に投資をスタートできる点が最大の特徴です。
投資はハードルが高く思われがちですが、数万円の範囲内で購入できる投資商品も数多くあります。
たとえば、新NISAの登場で注目を集めた「オール・カントリー」や「S&P 500」などの投資信託も100円から積み立てられるので、少額投資の対象とすることが可能です。
近年はスマートフォンのアプリなどを使って、いつでも好きなときに少額投資ができる環境も整っています。
もちろん、少額投資にはデメリットといえる側面もありますが、リスクヘッジしやすいことを考えると、投資初心者に適した運用方法といえるでしょう。
少額投資が初心者におすすめな5つの理由

少額投資が初心者におすすめな理由としては、以下の5点が挙げられます。
- 資金に余裕がなくても手軽に始められる
- リスクを抑えられる
- 精神的な負担がかかりにくい
- 実戦経験を積める
- 複数の商品に分散投資しやすい
少額投資のメリットを最大限に活かすためにも、まずは正しい知識を身につけておくことが重要です。
資金に余裕がなくても手軽に始められる
少額投資のメリットは、資金に余裕がなくても手軽に始められる点です。
ほとんどの投資商品には、それぞれ最低購入額額が設定されていますが、数百円からでも始められる商品は数多く存在します。
たとえば、投資信託なら100円から、株式でも1株単位で購入できる「単元未満株」を利用すれば数百円で投資することが可能です。
不動産クラウドファンディングなら、1万円程度でマンションや商業施設などの不動産に投資することもできます。
投資が一般化するなかで、資金面のハードルが低くなっているのは事実です。
余剰資金ができたときは、積極的にチャレンジしてみることをおすすめします。
リスクを抑えられる
リスクを抑えられることも、少額投資の主なメリットといえるでしょう。
投資額が増えるほど、リターン・リスクは大きくなるものです。
つまり、投資額を少額にとどめておけば、たとえ損失が生じたとしても、それほど痛手にはなりません。
10万円の投資で一度に何万円も失うケースは、よほどの相場変動があった場合だけです。
リスクヘッジの方法はさまざまですが、少額投資は難しい知識も不要なので、初心者の方は積極的に実践するようにしましょう。
精神的な負担がかかりにくい
少額投資のメリットには、精神的な負担がかかりにくい点も挙げられます。
大きな損失が生じないことを知ったうえで投資できるので、焦ったり、不安になったりして冷静さを失う心配がありません。
その結果、無理な取引を避けて安定的な運用がしやすくなります。
特に投資初心者の方は損失への抵抗感が強い傾向にあるので、まずは少額投資で資産の変動に動じないマインドを身につけていくことが重要です。
実戦経験を積める
投資の実践経験を積めることも、少額投資のメリットです。
投資の知識は本やインターネットなどで身につけられますが、実践経験の中で活かすことができなければ意味がありません。
実際に自分の資金を動かし、市場の仕組みや売買に適したタイミング、手数料の負担感などを知ることではじめて、投資家としてのレベルが上がっていきます。
デモトレードを活用するのもひとつの方法ですが、やはりリスクを負わなければ、緊張感やリスク管理の重要性を感じることは難しいでしょう。
少額投資での小さな経験の積み重ねは、将来的にまとまった資金で運用するときの大きな武器になるはずです。
複数の商品に分散投資しやすい
少額投資は、分散投資に適した手法といえます。
分散投資とは複数の投資商品に資産を分けて、損失のリスクを抑える方法のことです。
たとえば、数万円ずつ株式や投資信託などの異なる資産に投資したり、複数の銘柄に投資したりすることで、いずれかの価格が下落しても、ほかの投資先の利益でカバーできるようになります。
分散投資は、長期的な資産形成を成功させるために欠かせない考え方です。
まずは少額投資で実践し、その重要性を身をもって体感することをおすすめします。
少額投資のデメリット・注意点
メリットの多い少額投資ですが、以下のようなデメリット・注意点も存在します。
- 大きなリターンは期待できない
- 手数料が割高になりやすい
- 投資できる商品が限られる
- 雑な取引を繰り返しやすくなる
メリット・デメリットの両方を理解したうえで、効果的に少額投資を実践していくことが大切です。
大きなリターンは期待できない
少額投資では、基本的に大きなリターンを得ることはできません。
リスクとリターンは、投資金額に応じて変動するケースが一般的です。
そもそもの投資額が小さければ、リスクだけでなくリターンも小さくなります。
たとえば、年10%の高利回りを叩き出したとしても、投資額が1万円なら利益はたったの1,000円です。
短期間で資産を大きく増やしたい人にとっては、満足できない結果に終わってしまうかもしれません。
そのため、まずは少額投資で実践経験を積み、資金に余裕ができた段階で徐々に投資額を増やしていくことをおすすめします。
手数料が割高になりやすい
少額投資は、取引にかかる手数料の割合が大きくなる傾向があります。
証券会社や投資商品によっても異なりますが、売買したり、保有し続けたりする際には業者に手数料を支払わなければなりません。
1回ごとに固定の手数料がかかる場合は、投資額が小さいほど割高になってしまいます。
そのなかで頻繁に売買していると、利益よりも手数料が高くなり、「手数料負け」する可能性も出てくるでしょう。
少額投資では特にコスト管理が重要なので、手数料が低い証券会社や商品を選び、無駄な取引を避けることが成功のポイントとなります。
投資できる商品が限られる
少額投資では、選択できる商品が限られている点に注意が必要です。
多くの投資商品には最低購入額が設定されており、10万円以下の資金では投資対象から外れてしまうことがあります。
たとえば、通常の株式投資は100株単位で購入しなければならないので、基本的には10万円以上の資金力が必要です。
とはいえ、単元未満株や不動産を小口化した商品など、少額で投資できるような仕組みも数多く存在します。
よほどニッチな投資商品を選ばない限り、過度に気にする必要はないでしょう。
雑な取引を繰り返しやすくなる
少額投資では、雑な取引を繰り返してしまう傾向にあります。
少額投資では損失が生じても大きな痛手にならないので、一回一回の取引に対する心理的なハードルが低くなってしまうのです。
そして「失敗しても大したことない」と適当に取引していると、経験値は増えず、投資のモチベーションも下がってしまいます。
少額であっても、大切な資産であることに変わりありません。
失敗から学んで、次に活かしていく意識を持つことが大切です。
少額投資におすすめの手法12選
これから少額投資を始める方には、次の投資手法をおすすめします。
- 不動産クラウドファンディング
- 投資信託
- ETF(上場投資信託)
- REIT(不動産投資信託)
- FX
- 暗号資産(仮想通貨)
- 個人向け国債
- 単元未満株
- 株式累積投資
- ロボアドバイザー
- ポイント投資
- おつり投資
それぞれに異なる特徴があるので、自身の運用方針に適した手法を選択しましょう。
不動産クラウドファンディング
不動産クラウドファンディングは、複数の投資家が不動産ファンドに出資し、事業者が物件の購入・運用をおこなう仕組みのことです。
投資家は出資額に応じて、運用益の一部を受け取ることができます。
不動産クラウドファンディングであれば、1万円程度から出資できるので、少額投資に最適です。
多額の資金がなくても、不動産に投資できることは大きなメリットといえるでしょう。
| メリット | デメリット |
| ・運用を事業者に任せられる・投資家の資産が守られる仕組みがある・安定した運用益が期待できる | ・原則として中途解約は認められない・人気のファンドは応募が殺到する・運営会社の倒産リスクがある |
これから不動産クラウドファンディングを始める方には、不動産BANKの利用をおすすめします。
不動産BANKは、中古一棟収益物件の販売棟数全国No.1の実績を有する「株式会社ファミリーコーポレーション」が運営するサービスです。
首都圏の中古一棟収益物件を扱い、安定して年6%の高利回りを実現しています。
随時魅力的なファンドが立ち上がっているので、ぜひ公式サイトをチェックしてみてください。
投資信託
投資信託は、複数の投資家から集めた資金を元手に、プロの運用会社が株式・債券などに投資する金融商品です。
投資家には保有量に応じて、分配金が付与されます。
投資信託は100円からでも購入できるので、初めての投資先にぴったりです。
積立設定をおこない、無理のない範囲で毎月一定額ずつ投資していくスタイルが一般的といえるでしょう。
| メリット | デメリット |
| ・運用をプロに任せられる・簡単に分散投資ができる・銘柄数が多い | ・手数料(信託報酬)がかかる・発注時の価格と実際の取引価格にズレが生じることがある |
投資信託の各銘柄は、複数の投資先で構成されています。
つまり、1つの銘柄を購入するだけで自動的に分散投資ができるのです。
投資信託では少額かつリスクを抑えた投資が可能なので、初心者の方は選択肢に入れておくようにしましょう。
ETF(上場投資信託)
ETFは、証券取引所に上場している投資信託です。
基本的な仕組みは通常の投資信託と同じですが、取引所が開いている間、リアルタイムで売買できる点が最大の特徴といえるでしょう。
ETFの銘柄数は限られますが、基本的には数万円程度から購入できます。
| メリット | デメリット |
| ・リアルタイムの取引ができる・取引コストが低い | ・分配金の再投資機能がない・銘柄数が少ない |
ETFは、日経平均株価やTOPIX(東証株価指数)など、特定の指標に連動するように運用されます。
そのため、企業分析などにかけるコストが抑えられており、結果として取引手数料が低めに設定されている点が魅力です。
REIT(不動産投資信託)
REITは、投資家から集めた資金でオフィスビル・商業施設・マンションなどの不動産を運用し、その収益を分配する投資信託です。
銘柄にもよりますが、10万円以下の資金でもREITに投資できます。
多額の資金がなくても、手軽に不動産投資が体験できる点は大きなメリットといえるでしょう。
| メリット | デメリット |
| ・運用を事業者に任せられる・利回りが高い傾向にある | ・現物不動産投資のような節税効果はない・投資法人の倒産リスクがある・災害リスクや金利変動リスクなどがある |
REITには、利益の9割超を分配金に回すことで、事業者が税制優遇を受けられる仕組みがあります。
そのため、利益が積極的に還元され、利回りが高くなる傾向にあるのです。
FX
FX(外国為替証拠金取引)は、異なる国の通貨ペアを売買し、為替差益を狙う投資方法です。
保有期間中はほぼ毎日、通貨間の金利差(スワップポイント)が付与されるので、不労所得を形成することもできます。
FX最大の特徴は、自己資金の25倍までであれば、レバレッジを効かせて投資できる点です。
資金が少なくても大きな取引ができるので、積極的に利益を狙いたい方におすすめの手法といえるでしょう。
最低投資額はFX業者によって異なりますが、数万円の資金があれば十分始められます。
| メリット | デメリット |
| ・レバレッジを効かせた取引が可能・平日は24時間いつでも取引できる・「買い」「売り」のどちらからでも取引を始められる | ・損失のリスクが高い・為替変動の影響を受ける・資金管理が難しい |
レバレッジを効かせたFX取引は、ハイリスク・ハイリターンで知られています。
安易に手を出した結果、資産の大半を失っている人も多いので、資金管理には十分注意してください。
暗号資産(仮想通貨)
暗号資産(仮想通貨)は、オンライン上に存在するデジタル通貨を購入し、売却時の差益を狙う投資手法です。
代表的な仮想通貨としては、ビットコインやイーサリアムなどが挙げられます。
高額な仮想通貨は小数点以下の単位で取引できる仕組みが取られているので、10万円以下の少額でも、ほぼすべての通貨を購入することが可能です。
| メリット | デメリット |
| ・24時間いつでも取引できる・少額でも莫大な利益を狙える可能性がある | ・ハッキングリスクが高い・価格変動が激しい・情報収集が難しい |
仮想通貨の種類は、国内の取引所に上場している銘柄だけでも20~40種類ほどあります。
今後成長する銘柄に投資できれば、資産を数倍~数十倍に増やすことも不可能ではありません。
一方で価格が急落したり、価値がほぼなくなったりする可能性もあるので、あくまでも余剰資金の範囲で投資することが重要です。
個人向け国債
個人向け国債は、国が発行する債券を購入し、利子を得る投資手法です。
国が財政破綻しない限り元本割れしないので、利子の分だけ確実に利益を上げられます。
また、最低購入額も1万円に設定されているため、少額の資金でも無理なく投資することが可能です。
| メリット | デメリット |
| ・安全性が高い・1年後からは途中解約も可能 | ・リターンが小さい・中途解約すると利息が減る・インフレに弱い |
とにかく安全性を重視する方には、個人向け国債がおすすめです。
しかし、個人向け国債で大きなリターンを得ることはできません。
2015年8月現在、年利は高くても1%程度なので、10万円投資しても1,000円程度しか増えない計算です。
投資経験を積むための手法としては有効ですが、いずれ投資資金を増やしたり、ほかの投資方法に切り替えたりすることも検討する必要が出てきます。
なお、個人向け国債は以下の3種類に分かれているので、自身の運用方針に合わせて適切に使い分けましょう。
| 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 | |
| 満期 | 3年 | 5年 | 10年 |
| 金利タイプ | 固定金利 | 変動金利 | |
| 金利の下限 | 0.05% | ||
| 利子の受け取り | 年2回 | ||
| 購入単価 | 1万円単位 | ||
単元未満株
単元未満株は、通常100株単位で売買される株式を1株単位などの少額から購入できる商品です。
通常、株式は100株単位で取引するので、10万円以下で購入できる銘柄は限られてしまいます。
一方、単元未満株であれば、資金が少なくても国内外の有名企業の株主になれる点が最大のメリットといえるでしょう。
| メリット | デメリット |
| ・高額な株式でも無理なく購入できる・配当を受け取れることもある | ・取引手数料が割高になりやすい・株主優待を受けられない |
株式投資は、投資の王道ともいえる手法のひとつです。
市場の情報収集や企業業績の分析などを通じて、今後につながる汎用的な知識・経験を身につけられるので、単元未満株からでもチャレンジしてみることをおすすめします。
株式累積投資
株式累積投資は、毎月一定額を自動的に積み立てて株式を購入する方法です。
資金の少ない人でも計画的な長期運用が可能になり、平均取得単価を下げる「ドルコスト平均法」のメリットも享受できます。
銘柄選びさえ間違えなければ、複利効果による資産の増加も期待できるでしょう。
| メリット | デメリット |
| ・時間分散でリスクヘッジできる・手間がかからない | ・短期間で大きな利益は狙えない・手数料がかかる |
株式累積投資では、運用管理の手間が省けます。
仕事や家事で忙しく、不労所得の形成を目指している人にも適した投資手法といえるでしょう。
ロボアドバイザー
ロボアドバイザーは、リスク許容度や運用目的を伝えるだけで、運用方針に見合った投資先をAIが提案・実行してくれるサービスです。
「一任型」と「助言型」の2種類があり、提供されるサービスに以下のような違いがあります。
- 一任型:投資先の選定や資産構成の見直し、売買などの投資判断を一任できる
- 助言型:運用方針に合ったポートフォリオ・商品を提案してくれる
一任型は、最低投資金額10万円・積立金額1万円程度に設定されています。
助言型であれば、1商品につき100円程度から積立が可能です。
| メリット | デメリット |
| ・最適な資産運用をサポートしてもらえる・運用の手間がかからない | ・投資の知識が身につきにくい・手数料が高い傾向になる |
時間はかけられないけれど、とにかく投資を始めてみたいという方にはロボアドバイザーが適しています。
100%の成功が保証されているわけではありませんが、無計画に自己判断で投資するよりは、効率的に資産を増やしていけるはずです。
ポイント投資
ポイント投資は、クレジットカードや電子マネーなどで貯めたポイントを使って投資ができるサービスです。
現金を使わずに、投資や運用を体験できる点が最大の魅力といえます。
たとえ損失が出ても現金を失うわけではないので、資産形成の第一歩として試してみるのもよいでしょう。
| メリット | デメリット |
| ・現金不要で投資できる・面倒な手続きが不要で始められる | ・選択肢が少ない・手数料が割高なことも多い |
すでに利用している決済サービスで、ポイント投資を始められる可能性もあります。
ポイントの使い道に悩んだときは、ポイント投資に充てることも検討してみてください。
おつり投資
おつり投資は、買い物をした際のおつり分を自動的に積み立てて投資するサービスです。
たとえば、支払いが780円だった場合に1,000円との差額220円が投資に回されます。
日常生活を送る中で資産形成を進められるうえ、運用の手間がかからないのも魅力です。
| メリット | デメリット |
| ・投資の知識がほとんどいらない・運用の手間がかからない | ・手数料が負担になる・キャッシュレス決済などの利用が前提となる |
おつり投資は家計への負担が少なく、「気づいたら資産ができていた」という実感が得られやすい初心者向けの投資手法です。
長く続けるほど顕著な成果が表れるようになるので、今すぐにでもはじめてみることをおすすめします。
少額投資で失敗しないためのポイント

少額投資で失敗しないためのポイントとしては、以下の7点が挙げられます。
- 運用目的を具体的に決めておく
- リスク許容度を明確にしておく
- 余剰資金で投資する
- リターンを狙い過ぎない
- 長期運用を意識する
- できるだけ手数料がかからない方法を選ぶ
- 公的制度を活用する
投資の基本といえる知識なので、一つひとつのポイントをしっかりと押さえておきましょう。
運用目的を具体的に決めておく
少額投資を始める際には、まず「何のために投資をするのか」という運用目的を明確に設定しておくことが大切です。
ゴールがはっきりしていると運用計画が立てやすくなるほか、投資判断に迷うことも少なくなります。
「子どもが進学するまでの10年間で500万円貯める」「20年後の退職までに1,000万円用意しておく」など、いつまでにいくらまで増やしたいのかを具体的に決めておきましょう。
また、最終的なゴールを意識することは、モチベーションの維持にもつながります。
リスク許容度を明確にしておく
少額投資に踏み切る前に、リスク許容度を明確にしておくことも重要です。
自身がどこまで損失を許容できるのかによって、選ぶべき投資手法は大きく異なります。
たとえば、リスク許容度が低い人は、個人向け国債や投資信託などが選択肢に入ってくるでしょう。
一方でリスク許容度が高い人は、FXや仮想通貨にチャレンジしてみるのもいいかもしれません。
リスク許容度を超えた運用方法は、冷静さを失う原因になります。
不安やストレスを感じず、精神的に余裕をもって運用することを心がけましょう。
余剰資金で投資する
投資は元本割れのリスクがあるため、余裕資金を使うのが鉄則です。
少額投資であっても、生活費や緊急時のための資金まで運用に回すのは避けましょう。
完全に余っているお金だけを投資に充てれば、相場の変動に慌てて売買することも防げます。
まずは、毎月の収支状況を正確に把握し、余剰資金を洗い出すことから始めましょう。
リターンを狙い過ぎない
投資する際には、リターンを狙い過ぎてはいけません。
特に投資初心者は短期間で大きな利益を上げようと無理をしがちですが、高いリターンを求めすぎると、その分損失のリスクも高まってしまいます。
投資の世界において、リスクとリターンは比例関係にあることを念頭に置いておきましょう。
少額投資をしている間は、本格的な投資に向けた準備期間ともいえます。
目先の利益にとらわれず、「少しずつ着実に増やす」姿勢を貫くことが成功の鍵です。
長期運用を意識する
少額投資で大きな資産を築くには、時間を味方につけてコツコツ積み立てる長期運用が欠かせません。
長期運用のメリットは、不必要な売買を防げることです。
短期的な価格変動に惑わされずに長期で運用していれば、損失を被っても挽回できる期間が長くなり、運用成績も安定しやすくなります。
また、運用期間が長くなるほど、複利効果による資産の増大が期待できます。
取引タイミングをこまめに見極める必要もないので、投資にかける時間を十分に取れない人は、長期投資を基本に運用を進めましょう。
できるだけ手数料がかからない方法を選ぶ
少額投資は、手数料の負担がリターンに直結しやすい手法です。
取引回数が多いと手数料が利益を圧迫し、いわゆる「手数料負け」になりやすいので注意してください。
証券会社や銀行ごとに手数料体系は異なるため、入金・出金・売買手数料などを事前にしっかり比較検討し、なるべくコストの低いサービス・商品を選ぶことが大切です。
また、キャンペーンやポイント還元なども活用し、運用コストをできるだけ抑える意識を持ちましょう。
公的制度を活用する
少額投資で効率よく資産形成するためには、公的制度の活用が必要不可欠です。
主にNISAとiDeCoの2種類が挙げられるので、それぞれの制度概要を詳しく解説します。
h4:NISA(少額投資非課税制度)
NISAは、少額での投資を促進するためにつくられた公的制度です。
日本在住の18歳以上であれば、基本的に誰でも加入できます。
NISAの特徴は、投資の運用益がすべて非課税になることです。
通常であれば20.315%の税金が差し引かれますが、NISA口座を使って投資するだけで、運用益をそのまま受け取れるようになります。
NISAは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」にわかれており、以下のような違いがあるので適切に使い分けましょう。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限 | |
| 非課税保有限度額 | 総枠1,800万円(成長投資枠に限っては1,200万円が上限) | |
| 投資対象 | 投資信託 | 株式・投資信託など |
少額投資であれば、年間の投資枠を気にする必要はないでしょう。
投資信託に投資するなら「つみたて投資枠」、投資信託以外に投資するなら「成長投資枠」を選ぶので基本的に問題ありません。
なお、NISAではオンライン上で投資額を簡単に変更できるので、家計の変化に合わせた柔軟な運用が可能です。
h4:iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、老後の資産形成を支援するための私的年金制度です。
20歳以上60歳未満の国民年金被保険者であれば、原則として誰でも加入できます。
iDeCoのメリットは主に2つあり、1つ目はNISA同様、運用益が非課税になる点です。
約20%の課税を回避しつつ、効率的に資産形成を進められます。
2つ目のメリットは、掛金が全額所得控除になる点です。
年間の掛金総額をそのまま所得から差し引けるので、課税所得が圧縮され、所得税・住民税の節税効果が期待できます。
ただし、iDeCoの資産を受け取れるのは原則60歳以上からです。
どうしてもお金が必要な状況にあったとしても、引き出しは制限されています。
また、職業によって掛金上限が変わってくるため、制度内容をよく理解したうえで活用することを心がけましょう。
まとめ

少額投資は10万円以下の小さな金額で気軽に始められ、投資初心者がリスクを抑えながら経験を積むのに最適な方法です。
損失額を抑えられ、複数の商品への分散投資もしやすいため、長期的な資産形成の第一歩にぴったりな選択肢といえるでしょう。
上述のとおり、少額投資の方法は多岐にわたりますが、なかでも不動産クラウドファンディングがおすすめです。
不動産クラウドファンディングであれば、1万円程度から投資できるうえ、事業者に運用を任せられるので、特別な知識・経験を必要としません。
少しでも不動産クラウドファンディングに興味がある方は、ぜひ不動産BANKの公式サイトをチェックしてみてください。
不動産BANKでは、年利6%を狙える魅力的なファンドが随時立ち上がっています。
スマホひとつでサクッと会員登録ができるので、この機会に投資の世界に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。



